南城市百名地区 月桃の活用方法 再発見プロジェクトの小冊子を頂きました
南城市百名地区で、月桃再発見プロジェクト の小冊子を頂きました。月桃の活用方法 月桃茶 月桃染め 月桃の料理 月桃ロープ 月桃蒸留水 虫除け&消臭スプレー アロマ効果 陶 樋龍で、シーサーの置物を沢山見せてもらいました。第157回沖縄訪問(5)
百名地区の散策
百名伽藍で食事をした後は、
この近くをドライブして回ります。
百名伽藍の近くで有名なところといえば、
垣花樋川(かきはなひーじゃー)です。

沖縄は昔から、水に苦しんできています。
今のように水道施設がない時代は、天然の雨の水、
川の水、池の水、井戸の水などが生活の頼りでした。
そんなときに一年中水が堪える事がない、
地下水が湧いてくることは、とても幸運な事です。

今日駐車した場所は、
垣花樋川に下に降りていく場所です。
切り立った岩の細い道を、
足下に気を付けながら下に降りていくと、
垣花樋川があります。
歩いている内に滑りそうになったので、
ここで捻挫でもしたら大変と、
三人は降りていくのを中止しました。

月桃再発見プロジェクト
南城市の百名地区には、畑も、庭も、林も残っていて、
植物が元気に育っています。
中でも、好きな植物は、月桃です。
月桃は、熊笹よりも、もっと大きくした、
笹に似た葉をしています。
この月桃を使ってお餅をくるんだり、お魚を巻いたりします。

百名地区では、月桃を大切に育てているようです。
月桃再発見プロジェクトによれば、
月桃はすごい効果と、いろいろな活用法があるようです。
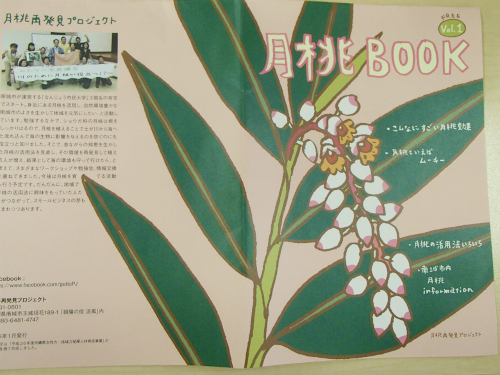
月桃の効果です。
葉:抗菌作用を生かして食材を包む、お茶として飲用する、
粉にしてお菓子やパンに混ぜる、
蒸留してして化粧品や防虫・消臭スプレーなどにも使われます。

花:5~7月に白い花が房のように咲きます。
月光に照らされた白い花が桃のようだという説があります。
実:秋に丸い2cmくらいのオレンジ色の実がなります。
乾燥させ、茶色くなったものを煎じてお茶にする、
胃腸の調子を整え、冷えを原因とする
諸症状に良いと言われています。
茎:成長した物で2m以上にもなます。
繊維が強いので、以前はサトウキビを
結束するものにも使われていました。
葉と同様に蒸留して、防虫・消臭スプレーや、
化粧水の原料になります。
根:肥満防止効果や、
抗菌作用など、様々な成分が含まれ、
医薬品原料などとして活用されています。
土にしっかりと根が張るので、土砂の流失防止や、
防風林代わりに畑の周りなどに植えられます。
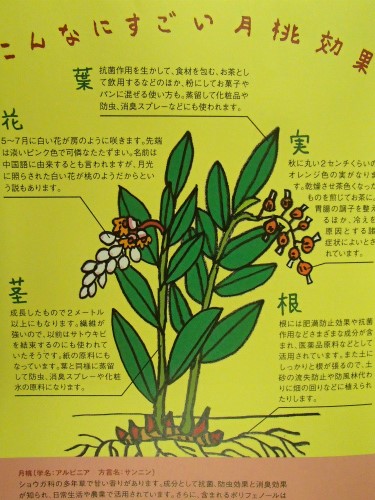
月桃の活用方法
月桃茶
月桃染め
月桃の料理
月桃ロープ
月桃蒸留水
虫除け&消臭スプレー
アロマ効果
根っこの力
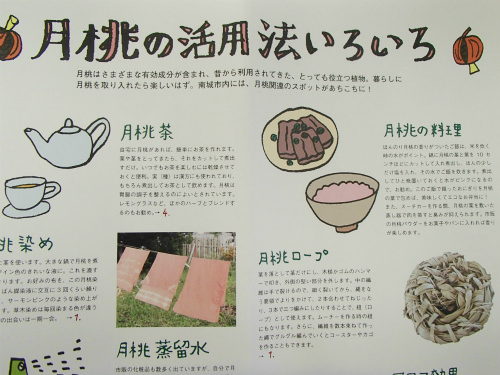
月桃と言えば、ムーチーです。
作り方は、餅粉1kg、砂糖300g、水760~800cc、
月桃の葉35枚(幅の広い方が良い)、結び紐35本、
①月桃の葉は綺麗に洗って水気を拭いておく
②もち粉、砂糖をボールに入れ、
水を加え、耳たぶの柔らかさにこねる
③2つのネタを月桃の葉の裏側に
1枚あたり50~60gずつ、小判型にして包む
④蒸し器に並べ、30~40分蒸したら出来上がり

月桃の葉を観賞していると、
焼き物釜のあるお店がありました。

その名は、陶 樋龍です。

どんな陶器があるのか、中に入って見せてもらいます。
入り口は蔓で覆われ、夏なら日よけになり、
花も咲き、自然のカーテンです。

陶 樋龍は、龍の置物が得意のようです。
シーサーと言われる龍の置物です。
沖縄では屋根において、魔除け代わりにされます。

中で対応してくれたご婦人は、
ここのご主人の奥様のようで、
親切に自宅で作ったお餅を勧めてくれました。
買わないのにお菓子だけ頂いて
、申し訳ないなぁと思いながら、失礼しました。

頂いたしおりには、
工房のご主人が書いた月桃の絵が入っていました。
大変お上手な絵なので、
焼き物よりこちらの月桃の絵があれば買いたいと思いました。

ご近所で見たのは、
陶 樋龍で製作してもらった鬼瓦を、
玄関に飾っていた瓦です。
置物では無くて、タイルのように平面で、
壁の一部として、はめ込まれていました。

百名地区の生活の小道を散歩していて、
陶芸のお店や月桃の
再発見プロジェクトに触れる事が出来ました。
百名地区は、落ち着いた沖縄らしい
雰囲気をもった素敵な地域です。
2016年1月31日(日)

