こよなき幸せ 幸せとは ブッダのことば― スッタニパータ /インド巡礼記
こよなき幸せ ブッダの教え ブッダのことば―スッタニパータ 幸せとは何か:家庭を築き、仕事に精を出し、人生も順調に歩んでる時、ふと心の中に、「これで良いのかな?何か大事な事を忘れていないかな?成る程と腑に落ちる様な真理を理解できてるのかな?」このように、ふとした疑問がどんどん膨らんできたからです。インド巡礼記【その16】
幸せとは何か インドでブッダの教えに触れました。

仏教にも「幸せとは何か」の定義があったんです。
今日は、ホテルを出てブッダの残した仏教について
地元のブッダガヤにある国際仏教会館を訪ね、
ブッダの教えを学ぶことにしました。
仏教は、世界三大宗教の一つで、
東南アジアを中心に仏教は広く伝播され、
今でも各国から仏教研究のために
研究施設がインドに作られています。
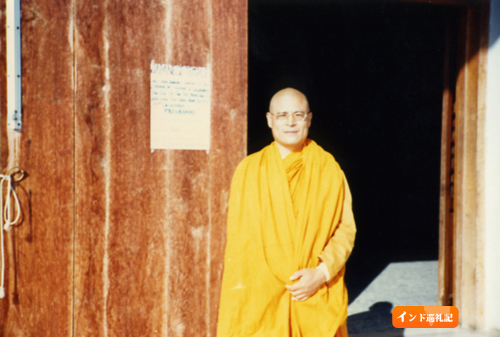 |
今日、会った修行僧は
日本からインドへ修行に来ている方で、
私の質問に対し、丁寧に答えて、
今まで分からなかったことを教えてくださいました。
私が尋ねたことは、
「無明(むみょう)」とは何ですか?
この世の中を暗くしているものは何ですか?」
という質問から始まり、
そして、「私を含めて皆さんが求めている幸せとは何ですか?」
というような法話を聞きました。
 |
無明とは、
文字通り明りが無いことですが、
仏教では、光が知恵を表し、
光が無いことは知恵が無いことを意味します。
知恵とは、学校で習う数学や理科がわかることが
知恵と捉えてはいません。
知恵とは、人として生まれたときからこれまで
何人もの人が経験してきた避けられない、
どうにもならないことを知ることです。
「こよなき幸せ」ブッダの言葉を残しています。
 |
こよなき幸せとは
こよなき幸せ 259:
諸々の愚者に親しまないで、諸々の賢者に親しみ、
尊敬すべき人々を尊敬すること-これがこよなき幸せである。
こよなき幸せ 260:
適当な場所に住み、予め功徳を積んでいて、
自らは正しい誓願を起こしていること、
-これがこよなき幸せである。
こよなき幸せ 261:
博学と、技術と、訓練をよく学び受けて、
弁舌巧みなこと-これがこよなき幸せである。
 |
こよなき幸せ 262:
父母につかえること、妻子を愛し護ること、
仕事に秩序あり混乱せぬこと、
-これがこよなき幸せである。
こよなき幸せ 263:
施与と、理法にかなった行いと、
親族を愛し護ることと、非難を受けない行為、
-これがこよなき幸せである。
こよなき幸せ 264:
悪を厭い離れ、飲酒を制し、
徳行をゆるがせにしないこと、
-これがこよなき幸せである。
 |
こよなき幸せ 265:
尊敬と謙遜と満足と感謝と
(適当な)時に教えを聞くこと、
-これがこよなき幸せである。
こよなき幸せ 266:
耐え忍ぶこと、温良なこと、
諸々の<道の人>に会うこと、
時々理法についての論議をすること、
-これがこよなき幸せである。
 |
こよなき幸せ 267:
修養と清らかな行いと聖なる真理を見ること、
安らぎを証すること、
-これがこよなき幸せである。
こよなき幸せ 268:
世俗の事柄に触れても、その人の心が動揺せず、
憂いなく、汚れなく、安穏であること、-これがこよなき幸せである。
こよなき幸せ 269:
これらのことを行うならば、
いかなることに関しても敗れることがない。
あらゆることについて幸福に達する。
-これが彼らにとってこよなき幸せである。
以上の259から269までの偈(ゲ)は、
「ブッダのことば」に著されています。
よく人は「幸せにしてね」と
花嫁に頼まれることがありますが、
幸せとは、「わかりました。
あなたを私は幸せにします」と簡単に請合うような
中身ではないことがわかりました。
ほとんど自分で自分の心を
コントロールしなければ無理であることがわかります。
従って、安易に「幸せにしてあげる」
とは言わないほうがいいようです。
 |
こよなき幸せ ブッダのことば 特に、心惹かれたのは、
268の『世俗の事柄に触れても、その人の心が動揺せず、
憂いなく、汚れなく、安穏であること、
-これがこよなき幸せである。』という教えです。
つまり、心を安静に保ち、
食べ物やお金、モノ、色欲、名誉などに
心がウロウロしなければ、
幸せに近づくことがわかりましたが、
しかし、わかったからといって悟るまでは
何十年の修行が要るようです。
 |
インドの周りの状況を見れば、
2500年前のブッダの亡くなった頃と
人の生活はどれだけ変わったのでしょうか。
諸々の事象は変わっても、
人間の行っていることや
幸せを求めようとする欲望は変わっていません。
 |
このように、今日は心をどのように保つか、
ということがどれだけ難しいか、ということを学びました。
よく言われることは
「心こそ、心もとなき心なり、心に心、心許すな」
と言われています。
自分のものでありながら、
自分の心を捉えられないで、
まるでウナギを掴むように
心はどこかに逃げていこうとしています。
心は誰のものでしょうか。

