メルスプランの成功 加盟店が支えた復活劇と、メニコンミルの戦略
投稿No:10468
メルスプランの成功とその裏側 加盟店の功績と メニコンミルの戦略
メニコン直営店 Miruグループ

サブスクリプションが当たり前となった現代。
コンタクトレンズ業界で最初に
サブスクを導入したのは、
いまから約24年前のメニコンです。
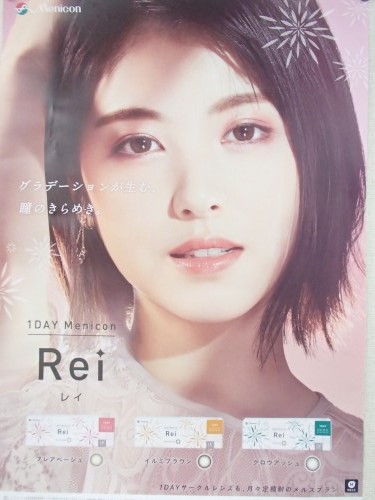
しかし、そこには単なる
“新サービス開発”では片づけられない、
メーカーと加盟店が
ともに作り上げたドラマがありました。
有力加盟店は、メルスプランに
参加するか、不参加か
その判断に自社の社運を賭けたと言えます。
そして今日、
メニコンが歩む新しい戦略が、
かつてのパートナーである
加盟店にどんな影響を与えているのか――。
そのことを、一度立ち止まって考えてみたいのです。

これまで、有力加盟店の経営者は
どのようにすれば、メルスプランが成功するのか
社長さん達は集まっては、
知恵を出し合ってきました。
■ 2000年前後——業界を揺るがした「価格破壊」

いまでは想像しにくいかもしれませんが、
2000年頃のコンタクトレンズ業界は
価格競争が激しく、
新製品が出てもすぐに値崩れ、
メーカーは利益を確保できない状況でした。
メニコンも例外ではなく、
当時は赤字が続いていました。
そんな中で生まれたのが、
のちに業界を変えることとなる
「メルスプラン」 でした。
■ 業界初の会員制システム「メルスプラン」の誕生
2001年、当時役員だった田中英成さんが中心となり、
レンズ破損交換無料
定期検査の体系化
サービス付帯型の月額課金
という、これまでにない仕組みを考案。
さらにメニコンは ビジネスモデル特許 を取得し、
他社が同じサービスを展開できない
“独自モデル” を築きました。
もちろん、当初は「定額でレンズを使う」
という新しい発想が
すぐに受け入れられたわけではありません。
しかし、メニコンが医師会・厚労省との
調整を重ねて合法性と安全性を確立したことで、
日本で初めての
コンタクトレンズサブスクがスタートしたのです。
■ メルスプランを全国に広げたのは「加盟店」の力だった

ここからが重要なポイントです。
メルスプランが成功できたのは、
仕組みが優れていたからだけではありません。
全国の優良加盟店が、
お客様に丁寧に価値を伝え続けたからです。
加盟店の社員の皆さんも一生懸命でした。

月額制への不安
“買い切り”の慣習
医療機器への慎重さ
こうした壁を一つひとつ乗り越えたのは、
地域に根付いた販売店でした。
「メーカーの発想 × 現場の説明力」
この掛け算こそが、メルスプランの躍進の本質だったのです。

その結果、メニコンは業績を大きく回復し、
2015年には東証一部に上場。
まさに“奇跡の復活劇”でした。
もしも、加盟店と加盟店の社員の
熱心な支援が無ければ、
メルスプランの成功は
無かったと言っても過言ではありません。

■ しかし、上場益は加盟店に還元されなかった

ここから先が、今日あまり語られない部分です。
メニコン復活の土台を支えた加盟店ですが、
株式公開による利益が還元されることはありませんでした。
もちろん株式上場は企業の自由ですし、
加盟店に株式を分配すべきという法律はありません。
しかし多くの加盟店が、
「あの苦しい時代を一緒に支えたのでは?」
「なぜ我々はメルスの成功の輪に入れてもらえないのか?」
という思いを抱えたまま今日を迎えています。
■ 上場後、メニコンが向かったのは「小売店の買収」

上場で得た資金を、
メニコンは次のステージへ投じます。
それが 小売店の買収によるグループ化 です。
エースコンタクト(激安店としてメニコンの競合だった)
富士コンタクト
シティコンタクト
ハマノコンタクト
などを次々と傘下に収め、自社直営店と統合して
「メニコンミル」グループ を形成しました。
製造・販売を統合するSPA(製造小売業)
Speciality Store Retailer of Private Label Apparel
これは業界戦略として見れば自然な流れです。
HOYAのアイシティに対抗するための
“直営網強化”とも言えます。
しかし――。
■ 長年のパートナーである加盟店は「ミル」に入れなかった

メニコンミルグループは
メニコンが買収した小売店を中心に構成され、
創業期からメルスを支えてきた
加盟店はその外側に置かれました。
メニコンミルは
買収した販売店を中心に組織され、
従来の加盟店はその外側に
置かれる形となってしまったのです。
さらに、メニコンは自ら
メニコンミルの新店舗を次々と展開しました。
HOYAが経営するアイシティ―グループに
対抗するグループです。
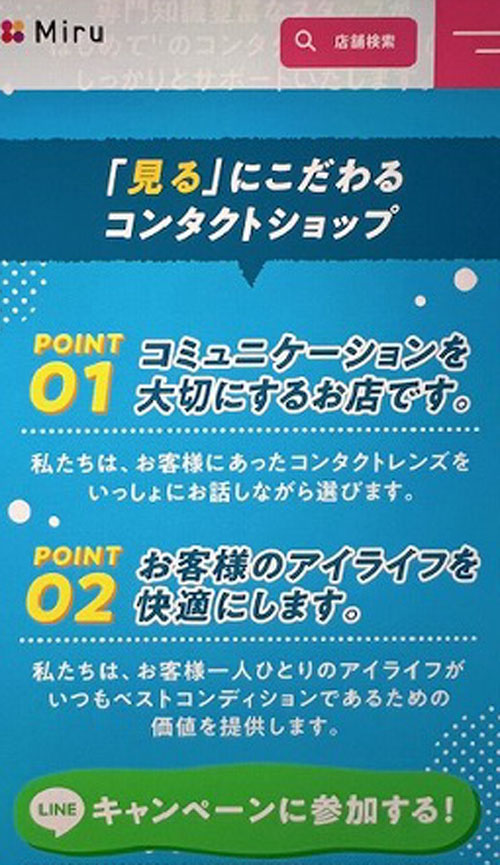
その結果、加盟店は
メニコンミルの一員として
共に歩むことはできず、
むしろ競合として対峙することになりました。
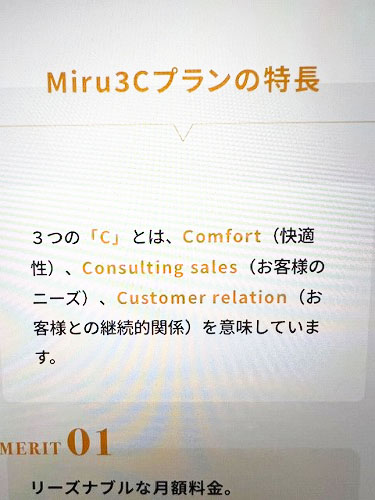
その結果、
メニコンミル(メーカー直系)
vs従来の加盟店(長年のパートナー)
という図式が生まれ、
地域によっては
同じメニコン同士で競合する状態 にもなっています。
これは、加盟店側から見れば
「仲間として一緒に未来を作れると思っていたのに」
「気づいたら競争相手になってしまった」
という複雑な思いを生むのは当然です。
■ メニコンに“敵意”はない。
ただ、もう一度「原点」を思い出してほしいのです
このブログは、メニコンを
批判するために書いているわけではありません。

むしろ、
日本の視力の健康
医療機器の適正利用
コンタクトレンズの未来

を真面目に考えてきたメーカーだからこそ、
これまでの歴史の中で生まれた
“溝”に目を向けてほしいのです。
サブスクの成功には
加盟店の努力が不可欠だった。

メニコンの復活を
一緒に支えてきた歴史がある。
そして、小売店を買収して
グループ化するという新戦略 SPA(製造小売業)は、
加盟店との関係を弱くする危険もはらんでいます。
今こそ、
「メーカー × 加盟店」
の理想的なパートナーシップをもう一度考え直す時期なのではないか?
という問題提起をしたいのです。
経営戦略の視点から見ても、
こうしたやり方は
決して良いものとは言えません。
なぜなら、メニコンを支えてきた加盟店を
排除することは、信頼していたパートナーを
敵に回すことにつながるからです。
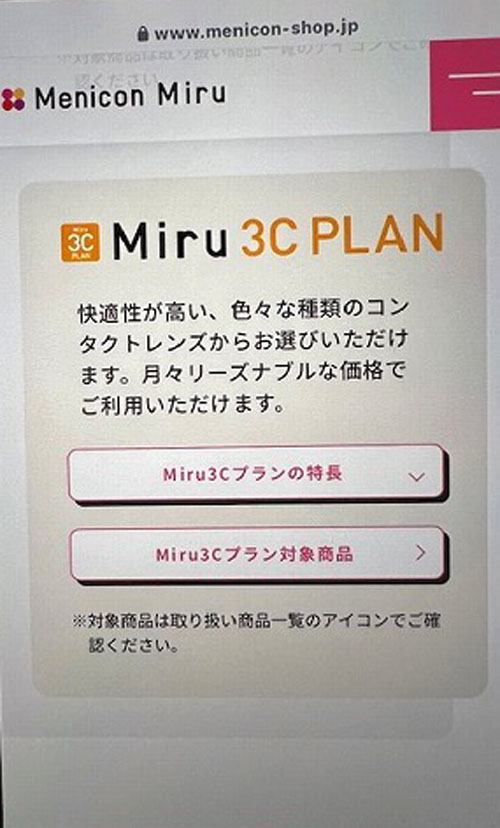
これは単に人間関係の問題にとどまらず、
企業にとって最も大切な
「ブランドの信頼」を揺るがす行為でもあります。
また、本来であれば
メーカーと販売店は協力し合い、
業界全体を発展させていく
補完関係にあるはずです。
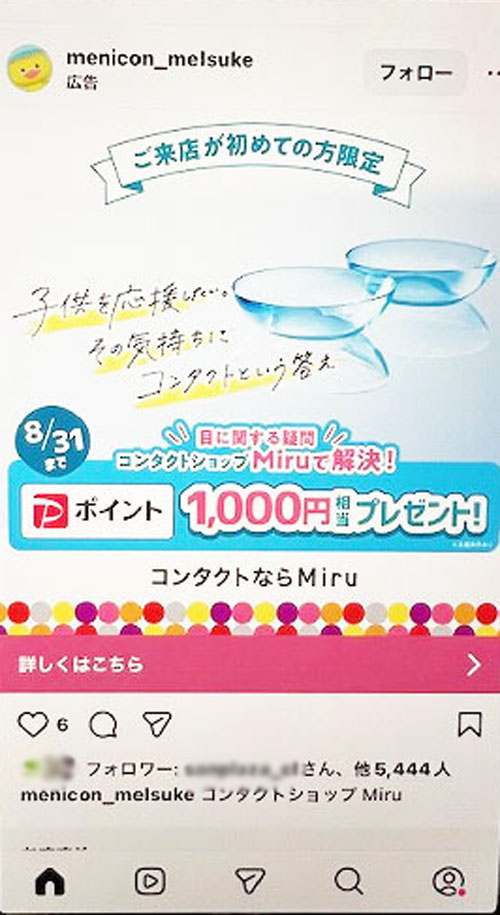
それが「メーカー対加盟店」という
対立構造になってしまえば、
業界全体の力を弱め、
結果的に海外メーカーなど他の競合に
有利な状況を作り出しかねません。
■ 業界の未来のために、再び「共創」を
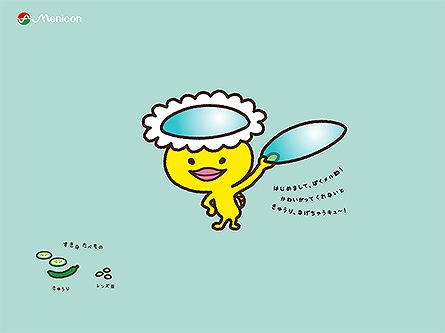
HOYA直営ののアイシティーや
海外メーカーが勢力を増す中、
日本のメーカー・販売店が
対立するのは得策ではありません。

製品を作る側
お客様に届ける側
本来この二者は、
補完し合ってこそ業界を強くできる存在です。
メニコンがもう一度、加盟店との信頼を大切にし、

業界全体の発展のために
手を取り合える未来が来ることを願っています。
メルスプランの成功は、“メーカーだけの成功”ではなかった。
その事実を、今あらためて共有したいのです。

2025.11.24

